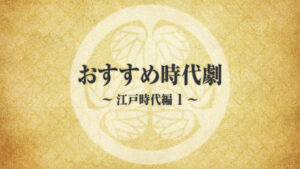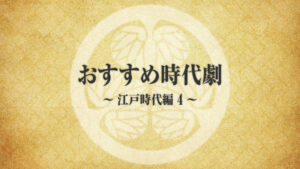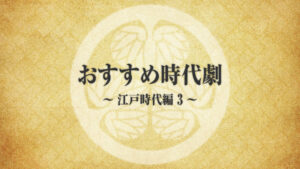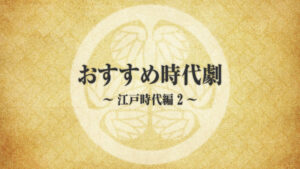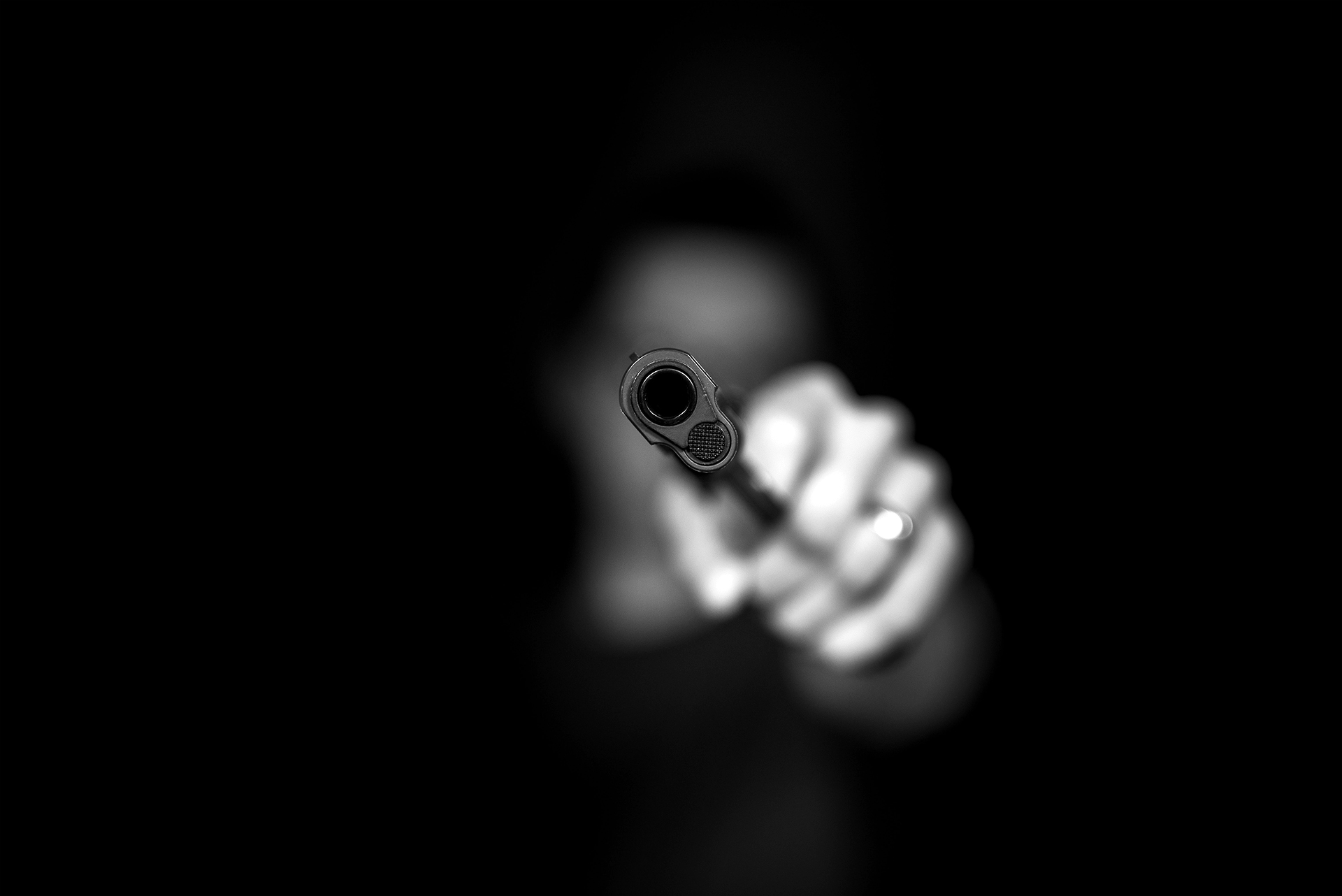
この記事にはネタバレがあります。
実在した暴力団の権力闘争をモデルにした娯楽映画<シリーズ全5作>
この記事は基本的に第1作目の内容を中心に書いていきます。まずはおさらいとして簡単にシリーズの概要を。
この「仁義なき戦いシリーズ」は、作家・飯干晃一原作のノンフィクション小説を1973年から1974年にかけて製作された東映実録ヤクザ映画です。
戦後の広島・呉市で実際に起こった抗争事件を元にしており、これは実在したヤクザで当事者のひとりであった美能組組長・美能幸三の獄中手記を軸に飯干晃一が実話小説として落とし込み、週刊サンケイで連載されていました。
これまでのいわゆる義理人情をうたった任侠映画という枠を外し、裏切りや暗殺などアナーキーなヤクザの世界の壮絶さがリアルに描かれています。
戦後の暗黒社会を臆することなく描写し、戦後史としての側面も持ち合わせ、その当時その世界でしか生きる事ができなかった若者を中心に語られた、「青春群集活劇娯楽映画」です。
オリジナルシリーズは全部で5作品
たった2年のうちに5作品が製作され、日本映画史に残る実録ヤクザ映画の最高傑作として今も語り継がれる人気シリーズです。
オリジナルシリーズのタイトル順と公開年は次の通り。
- 仁義なき戦い(1973年1月)
- 仁義なき戦い 広島死闘篇(1973年4月)
- 仁義なき戦い 代理戦争(1973年9月)
- 仁義なき戦い 頂上作戦(1974年1月)
- 仁義なき戦い 完結篇(1974年6月)
上記5部作はオリジナル。これ以降は新シリーズや別の監督作品として公開されました。

いまだ魅了し続ける…脚本・テーマ曲・映像演出
なぜ「仁義なき戦い」は時代・世代を超えて支持される人気作品となったのか。海外でも公開されており、クエンティン・タランティーノなどその作風に魅了された映画関係者や一般の国外ファンも多いです。
脚本とテーマ曲
この作品を“リアリティと娯楽の映画”として組み込んだ脚本の笠原和夫。取材と資料集めを徹底的におこない、専門用語の活用やヤクザの世界における人間の弱さや狡賢さ、卑しさ醜さといった血生臭い展開を娯楽用へデフォルメさせた構成が、実録娯楽映画と言われる所以かと感じられました。
とにかくストーリーが面白いです。テンポよく進み、会話の斬り合いも迫力があり、その会話もドスの効いた広島弁。初見は意味がわからないかもしれませんが、雰囲気だけでも充分伝わってきます。少しではありますが、広島弁のことも後述しているのでチェックしてみてください。
テーマ曲は今の若い人も聞けば「知ってる!」というほど、いまだにテレビ番組等で使用されているほどキャッチーでインパクトがあります。効果音としても使いやすく、また実際使われているため「仁義〜」を全く知らなくても曲だけは知ってるという人も多いかもしれません。
曲自体は複雑なものではなくシンプルなメロディですが、力強く勢いがあるので内容ととてもマッチし、人によっては仁義=このテーマ曲という人もいるぐらいです。余談ですが、携帯電話の上司からの着信音をこのテーマ曲にしている人も一定数いました。その人達にとって“仁義なき戦い”だったんでしょうね。
妥協しない深作監督
シリーズを通して監督は深作欣二です。
監督の特徴のひとつは暴力描写で、大量の血しぶきや斬られた腕や指が飛び交うシーンをダイナミックに演出しています。また、商店街や駅などの外ロケでは、今ではほぼ無理であろうゲリラ撮影(無許可撮影)で行われているものもあるそうで、かなり荒々しい映像になっています。
その撮影の仕方は、隠しカメラや手持ちカメラを持って役者を捉えていくため、ニュースのようなドキュメンタリーのような映像となり、襲撃シーンなどでは実際の事件もこういう感じかなとリアルに想像できたり、自分がその当事者(襲撃者)のような気になりながら観ることができます。これもまた作品の生々しさに拍車をかける演出となっています。
手持ちカメラの揺れ具合が凄まじく、なかにはカメラ酔いをしてしまう人もいるかもしれませんのでご注意を。
そしてもう一つはカメラアングル。劇中、酒井(松方弘樹)が有田(渡瀬恒彦)のところへ向かうシーンではハイアングル・ハイポジションでの撮影があったり、新開(三上真一郎)と有田の喫茶店での会話では、ポジションはアイレベルで正面からではなくサイドからの撮影をしています。
これは、あたかもジャーナリストが隠し撮りしているような、もしくはそこに偶然居合わせて恐る恐るも目撃してしまったような臨場感があり、いま自分がそこに居合わせているような感覚になります。
画角におさまっているもの全てに徹底してこだわり、深夜まで何度もリテイクを繰り返して撮影もしたそうで、背景や小物など全てにおいて妥協せずこだわり抜いた映像になっています。
後世にも語り継がれるほど製作陣の素晴らしい仕事ぶりが発揮されているので、上で述べた点やそれ以外の箇所にも注目して観てもらえたら嬉しいです。

個性派揃いの俳優陣が演じるキャラクター
出演者は主役の菅原文太はもちろん、その他の俳優陣もこれでもかというぐらい個性派揃い。今見ると、という事ではなく当時からすでに“濃い”メンツです。ここからは第1作目での気になった登場人物・俳優を数人紹介します。
広能昌三(菅原文太)…主人公。基本的に穏やかだが、いざとなるとやる時はやる性格。信頼も厚い。
菅原文太演じる広能は仲間意識がとても強く、恩義に忠実。自分の命の危険を顧みずに進んで関わっていきます。それ以外では互いに“君付け”や“ちゃん付け”で呼んだりと、意外と温和で大人しくギャップを感じる人柄です。キレたりすると我先にと突っかかっていきますが、意外と思慮深く冷静な考えも持ち合わせています。
若杉(梅宮辰夫)との関係性が好きなのですが、台詞通り若杉の兄貴について行くことが出来ていたらと思わずにはいられませんでした。
坂井鉄也(松方弘樹)…貫禄充分。若衆を引っ張り、組をひとつにまとめようと時には親父にも意見する。
松方弘樹演じる坂井鉄也はひたすら怖さ・カッコ良さを感じるキャラ。当初は酒井が主人公だったというのも納得です。親父との対決は名シーン・名台詞として好きな人も多いはず。自分が殺されると思い「ゥヒィィ!」と叫んでビビりまくる場面も必見で、坂井の内面・心情が分かりやすく伝わってきました。
若杉寛(梅宮辰夫)…広能と兄弟の盃を交わす。まさに「兄貴」と言える存在。
若杉は所属する組が違うにもかかわらず兄弟の盃を交わした広能の常に味方であり、自身の親父に反抗してまで広能の為、組の為に奔走する姿は演じた梅宮辰夫自信を含め、「兄貴」だなと思わせられます。もっと観ていたかった存在です。
有田俊雄(渡瀬恒彦)…ギラギラしすぎ。反抗心・野心が強く、坂井が相手でも一歩も引かずに対立する。
ある意味個人的に一番気に入ったキャラが有田です。初登場シーンでは渡瀬恒彦と気づかなかったぐらい衝撃を受けました。対立しているせいもあって表情や態度が凄まじく凶暴で、撮影なのに松方弘樹らと本当に殴り合いを始めるんじゃないかと思う程です。割と早く退場となったのが非常に残念でした。
槙原政吉(田中邦衛)…気の弱いコメディリリーフかと思ったが…
田中邦衛の槇原は正直ノーマークでした。迫力のあるシーンがそれほど多くなく、土居組を襲撃しようと話し合う中でのコントのようなやり取りにおもわず笑ってしまい、ただの気弱なギャグ担当かと思ったほどでした。実は立派なヤクザでした。気弱なりに。
山守義雄(金子信雄)…金稼ぎに執着。情けなさの裏で全体の流れを把握している策略家。
この第1作目でとにかく一番イラッとしたのが金子信雄の山守です。金に執着し気弱で情けない組長になぜみんなついていくのかと(実際に殆どの組員は良く思ってなかったですが)。保身のために子分を自身の掌の上で弄び、対立・裏切り・殺し合いと、争いの火種を作り大きく凄惨になるよう仕向けた策略家ぶりは腹立たしく、よくもやってくれたなと、ため息が出ました。
その他にも
ギラギラし過ぎている若かりし頃の大御所役者陣が熱演・怪演したため、すぐに退場となる登場人物でも忘れられないほど存在感たっぷりです。
その他にも、格さんで有名な伊吹吾郎(上田透役)、“悪代官”名和宏(土居清役)、大部屋俳優の川谷拓三・志賀勝や、同じく大部屋俳優で“5万回斬られた男”の福本清三(クレジットは福本清二)など、脇役もいけいけドンドンで演じているので、出演者全員の名演をぜひ観てほしいです。
専門用語や広島弁が飛び交う名言の数々
劇中ではほぼ広島弁で会話がなされ、隠語や暗喩の表現が多々出てきます。それがまたこの映画の魅力のひとつです。ここから幾つかその方言・用語を紹介します。
- 金筋=筋金入りの極道
- 盆・盆ござ=賭場・賭場で使うござ
- サツ=ポリ公=警察
- 天ぷら=衣→学生服、偽学生、天ぷら学生
- ポン=ヒロポン=覚醒剤(Philopon…「労働を好む」のギリシャ語由来だとか)
- カスリ=掠り、上納金、みかじめ料
- ゴロ=ステゴロ=素手喧嘩
- チンコロ=密告(サイコロ賭博のチンチロリンの俗称として使われることもある)
- こまい=小さい
坂井「親父のケツのこまいのはわかっとったが、考えすぎよ。」
- こんな=われ=おどりゃ=おまえ、こんなら=おどれら・おどりゃあ=おまえら
坂井「こんな、道具持っちょるんか?」
土居「山守!ワレはようも俺の裏をかいてくれたのう!」
山守「こんならにどれほどの商売ができるんなら。」
- そがいに=そんなに
広能「そがいな銭、でるとこありゃあせんです。」
- 〜のう=〜な、〜ね(協調的な意味合いのイメージで)
山守「のう!わしを助ける思うて、頼まれてくれ!」
- 旅=他所・他(他の所へ行く等、身を隠すといった意味合い)
坂井「わしはこれから旅打つけんのう」
- 〜じゃけん・〜じゃけぇ=だから
山方「昌ちゃん、もしこんなが殺ったら、こんなには前(前科)があるんじゃけん。」
- 〜つかぁさい・〜つかえや=してください
広能「わし、指詰めますけん。それで話つけてつかぁさい。」
まとめ
各々が友達のため仲間のために自身を犠牲にしたり、時にすれ違い傷つき傷つけられ、過去を後悔し未来を憂い、それでも自分の想いは貫こうとしつつ悩み・葛藤する様は、言ってみれば青春群像劇なんだなと感じました。ただ、背景があまりにも血生臭いものではありますが……
まずは一度サッと観てみることをお勧めします。
方言の意味や相関図など分からない場面はあるかもしれませんが、テンポ良くストーリーは進んでいくのであっという間でしょうし、なんとなくでも雰囲気は掴めると思います。俳優陣の熱演をただ観るだけでも良し、当時の雰囲気やヤクザの世界がどういったものなのかをただうっすらと感じるだけでも良いと思います。
今は令和の時代となり、ヤクザの規模自体はどんどんと縮小していますが、それでもヤクザによる傷害・殺人等の事件は起きています。
この映画自体はヤクザとその世界を美化・美談にしたものでは決してありません。実録・実話を元にとうたってはいるものの、あくまで娯楽映画の範疇です。むしろ暴力に対して強い批判を込めて製作された映画です。血や暴力表現が苦手な人には厳しいかもしれませんが、あまり身構えずに観てもらえたらと思います。